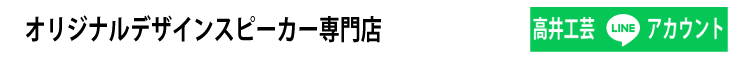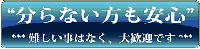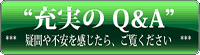アメリカンサウンドと言えば、JBLに代表されるドライでメリハリのある音、特に低音が強くないといけないらしい。それに対してイギリスでは、これもタンノイやハーベスなどが代表的で、 ぶ厚い中域音、少し霞がかかった雰囲気を作るのが上手い、そんな印象。
デンマークでは、世界のスピーカーユニットの殆どを占めていた時代が有ったほど、スピーカー作りでは世界の中心とも言え、 華やかで鮮明な音は、聴く人を楽しくさせるそんな印象です。あのJBLやインフィニティ―ですら、デンマークのメーカーからOEMを受けていたほどです。 変わったところでは、あのベルリン交響楽団を持つドイツでは、クラッシックに非常に厳しく、その耳は全てを再生しきっていなければ納得が行かない文化を持ち、 微細な音の先端まで表現しきる、そんな音を好むようです。 ですが、日本人にはさすがにきつく聴こえてしまい、これも好き好きではないでしょうか。
また、フランスなどは、あのハーベスのユニットを作っているメーカーが有ったりで、概ねイギリス+デンマークの様な印象でしょうが、今は元気なスピーカーメーカーが見当たらず、 特徴を表現するのは難しく思います。ノルウェーもデンマークメーカーを意識したようなメーカーが存在します。
上記の全ては、私の独断の意見ですので、当然異論を唱える方は多いと思います。
他には、当然日本、韓国、世界のユニットの90%以上を生産する中国、インド、インドネシア、イタリア、スペイン、ベルギー、スイス、カナダなどと言った国々が、 良質なスピーカー(オーディオ機器)を開発しています。
ですが、上記の4か国の様に、その国の好みや特徴が全く見えてきません。日本の場合はどうでしょうか? 過去にも現在でも優秀なメーカーが、多くの良質な音響機器を研究開発しています。では、日本の音とはどの様な感じでしょうか? これまで、その事を考える余裕はなく、択一的な音作りではなく、多くの表現を自由にユーザーが選べる、それで良いように感じていました。 ですがやはり、JBL(アメリカ)的とか英国風とか、他の文化やその国の国民性を模している様にも感じます。 これまで、日本の音を考えその様な製品づくりをして来たメーカーが思い当たりません。(自分が知らないだけでしょうが)
そんな事も含めて、何故自分はいつもこの「音」になるのか合わせて考えてみました。
日本の伝統音楽、例えば雅楽などは、室内の演奏ではありません。能舞台も基本は屋外ステージです。今で言うコンサートホールは日本にはなかったのでは。 祭りのおはやしも外ですし、和太鼓もそうです。温暖な気候に恵まれ、屋外の開放的な環境を自由に扱えた日本は、北欧の様な厳しい環境ではなく、 他の欧州の様に、鉛色の雲に覆われる時間が長い場所でもありません。 更には、琴や尺八等でも、場所は屋内でも、日本の建築は柱構造ですので、晴天(温暖)であれば全ての扉を空け放ち演奏する光景を思い浮かべます。 その様な屋外での環境を考えると、どこまでも音は広がりはるか先へ抜けて行きます。
また、世界的にも水に恵まれた国土を持ち、軟水の澄んだ水が豊富存在します。わさびの文化も、それなくしては存在しなかったものです。 挙げて行けば限がないのですが、その様な事から、繊細で透明感があり、澄んだ音がどこまでも抜けて行く、そんな音がこの国らしさではないでしょうか。もちろん、そんな簡単な話ではないでしょうが、いたずらに長文になることもあり、だいぶ割愛しています。これも、私の思い込みなのかもしれません。
いつも心掛けている事は、その透明感と限りない解放感で、無意識にでしょうがその答えと近いところを追求してきたのかもしれません。
「日本の音」を十分に再現(表現)する事は大変難しいのですが、日々少しでも近づける様努力しています。 今有るラインナップもその一部は表現できていると思いますが、特にYosegi-LやHC-TX400は、日本の音の入り口位には来ていると感じています。